みなさんこんにちは。精神科看護から少し離れているmizuki@おぬです。
そうなんです、今少し離れてるんですよね・・・精神科看護から。まあ、また元に戻りたくて現在あれこれ動いております。
昔は病棟なんて嫌だったんだけどな~、また病棟に戻ろうとしてるなんて不思議なものです。
さて、今回は毎月読んでいる医学書院「精神看護」2019年9月号の感想です。いや、ちょっと前にTwitter上で精神看護のアカウントに勝手に感想文なんかを送りつけてたんですが、今回はちょっとビジュアル的に見てほしいものもあり、フラクタルで書くことにしました。
さてさて、今月号はこんな感じです。
精神看護届いた!
また勝手に感想を送りつけることやっていいですか? @seishinkangogo さん? pic.twitter.com/ONXydzlrJL— mizuki@おぬ 9年目看護師 (@c_mikzuki) September 12, 2019
すみません、今回は感想をフラクタルで書かせていただいてます。
そして今回の特集「グラフィックレコーディング」。
文字や言葉ではなく「絵」として表現をすることで、精神疾患を抱える患者さんの心の内面を表現できるし、そもそも普通の会議などでも意識の統一ができる非常に有効な手段とのこと。確かに絵で書くことで、誰もが共通の考えを持つことができる。「身体の表面に黒い筋が入っている動物」と言ってもパンダ、キリン、シマウマが思い浮かぶように、みんな文字や文章から得る情報は様々。それを統一できる手法ですね。
ただね、実はこの前日。ライターの白石弓夏さんと食事した時に「僕は絵が下手」という話題で盛り上がり、そこで書いた絵がこれ。
おぬさんが書いたレア絵とごはん。
・特製キッシュ
・宮城定義山の三角定義油揚げ
・しょっつるだし茶漬け pic.twitter.com/tPWnbtvKRg— 白石弓夏@看護師兼ライター (@yumika_shi) September 11, 2019
どうでしょうか(笑)これ、左手のものは手を書こうとしたんですが、花束になりました(笑)
こんなレベルの私、グラフィックレコーディングなんて一番不得意だってことがよくわかるじゃないですか!!(笑)
でも、手段としてはとても有効だなと思うし、僕も普段から簡単なことぐらいアイコンで伝えたいなと思ってたし。
精神看護の作り方でとても良いのが、最初に「こうやるんだ」っていう結果を見せて、その後にやり方を見せるのよ。だから読み進めていくと、グラフィックレコーダーの清水淳子さんによる「人間を描けるようになろう」講座があるんです!
でも、僕のレベルは棒人間にも程遠い・・・けど、真似て書いてみた。
人間の書き方を精神看護読みながら練習してる。
お!描けた!!! pic.twitter.com/QxjPLx2Gz6
— mizuki@おぬ 9年目看護師 (@c_mikzuki) September 13, 2019
めっちゃ本を読みながら、iPadで書いてみた。
すると・・・
ナイスです◎! https://t.co/CUXmGz8XE9
— 清水淳子 / JUNKO (@4mimimizu) September 13, 2019
おおっ!!!!先生からコメントいただいた!!
これ!これを見せたくて、今回はフラクタルに感想を書いたんです(笑)
ぶっちゃけさ、一人の人が主人公であるなら、グラフィックレコーディングできる!!
(ちなみにiPad9.7インチ+ロジクールクレヨン+ペーパーライクフィルムにて描きました)
グラフィックレコーディングの良いところは、いろんな人の意見を集約できるし、問題の再定義がしやすい。異なった意見が出た場合はその人がどこの部分に異なった意見を持っているかがわかりやすい。そして絵と矢印、コメント(トピックの塊)を使うことでとてもわかり易く表現できる。
この先は、ぜひ精神看護9月号をご購入ください。
あとは、対談の特集で組まれていた「はじめての精神科」の著者、春日武彦先生と「精神疾患を持つ人を、病院でないところで支援するときにまず読む本」の著者である小瀬古伸幸先生との対談がとても面白かった。僕は「はじめての精神科」は精神科に入ってすぐに購入した本で、何度も何度も読み直した本。地域でも病棟でも使える本の著者と、在宅での支援のリアルな対応の仕方が書いてある本の著者が対談しています。本当、この2冊さえあれば自信を持って精神科訪問看護とかできる!!
あとはいつもの「うんこあるある」である塩月玲奈先生の連載。患者さんの日々の生活から実は排便が難しいんじゃないかなという話は勉強になりました。
山下隆之先生の「精神科仕事術」では「精神科看護だからこそ、看護の基本に立ち返る」というフレーズがすごくよかったです。本当、セルフケアに課題の多い患者さんは多いし、そこを解決することで退院へ導くことができる事例は私も何度も経験しました。初めて精神科に入職して慣れてきた時期だからこそ、振り返ることが大切っていう記事を書けるのは本当にすごいなと。ベテランになっていけば行くほど初心を忘れませんか?私もこういう振り返りのできる先輩になりたいです。
長々と書いてしまいましたが、感想終わり!
また次回も書きますよ!
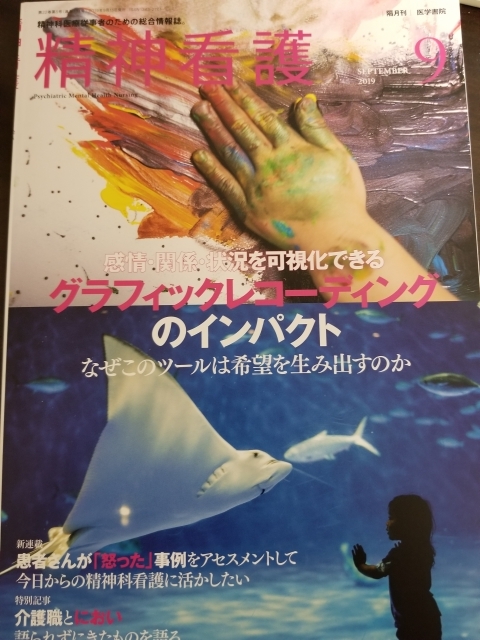
コメント